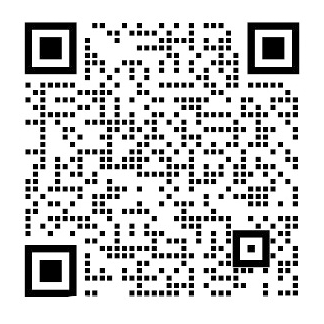菓銘から見た和菓子の意匠と四季开题报告
1. 研究目的与意义
キーワード:和菓子、意匠、菓銘、季節感
和菓子は、日本の伝統的製法で作られた菓子で、季節ごとにさまざまな種類がある。特に和菓子の神髄ともいわれる「上生菓子」(主菓子)は、自然の移り変わりを美的に表現したもので、茶の湯の伝統とともに長い歴史があり、今日でも日常生活に欠かせないものとなっている。和菓子を味わうことで季節を感じ取り、生活を楽しむのが日本の暮らしの伝統である。
それでは、和菓子における季節感とはどのようなものなのか。それはどのように造形され、菓子として供されるのか。四季折々の和菓子は、その色や形で時季が表わされるが、実は、和菓子にはその種類の名前だけでなく、それぞれに「菓銘」(菓子銘)と呼ばれる名前がある。「山路の秋」「春の錦」など、菓銘は優雅で奥ゆかしいものがつけられている。四季折々に表情を変える和菓子は、菓銘によってより一層味わい深いものになる。この菓銘を通して和菓子の多様な意匠や造形、そして日本人の自然観や生活観、美的意識を明らかにするのが本稿の目的である。
2. 国内外研究现状分析
国外部分:和菓子は、日本人の日常の中に深く根付いている。年中行事をはじめ、さまざまな儀式や儀礼などとも密接にかかわっている。それゆえ日本では、和菓子についての本や研究はたくさんある。Amazonで検索すると「和菓子」に関連した本は数百冊に及び、ロングセラー書も多い。例えば、青木直己『図説 和菓子の今昔』は、和菓子の起源と発展を述べたもので、和菓子の持つ文化的な側面も詳述している。中山圭子『事典 和菓子の世界』は、その名の通り事典で、和菓子の素材から製法、名称、用語などを写真付きで網羅的に解説し、奥深い和菓子の世界に親しむガイドブックのような内容となっている。他の類書も総じていえば、和菓子の製法や素材、歴史や意匠、和菓子の季節感などを解き明かすものが多い。しかし、いずれも菓銘の紹介はあっても部分的で、菓銘の意味や由来については十分論じられていない。
国内部分:近年、日本の文化や伝統への関心はさまざまな面にまで広がりをみせている。和菓子に対しての研究も少なくない。例えば、「从『和菓子』包装看日本包装的設計特色」は、和菓子そのものではなく、包装デザインの特色を考察したものである。「感悟日本伝統之美『和菓子』」は、和菓子から日本の伝統美を探っている。「虎屋和菓子:五个世紀的前世今生」は、虎屋という老舗を通じて和菓子の歴史を明らかにしている。和菓子から日本の文化や伝統のありようを見る研究が多いが、和菓子の意匠や製法などに触れたものは少なく、菓銘についての論考はほとんどみられない。
3. 研究的基本内容与计划
目次:
はじめに
第一章 和菓子の歴史と種類
4. 研究创新点
本稿は「菓銘」を手がかりに、いくつかの代表的な和菓子の例を挙げ、和菓子の名前に込められた意匠と四季折々の日本の自然美を検討する。
和菓子の名称だけでなく、その形、色、材料、製法、意匠、季節感、行事との関係なども合わせて紹介する。
必要に応じてそれぞれの和菓子の写真や図を添付する。
课题毕业论文、开题报告、任务书、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。