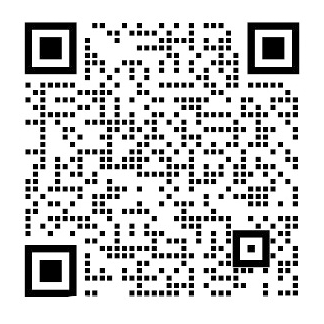日本茶道及其对中国的茶文化的借鉴意义开题报告
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)
「茶の美学」 谷川徹三 淡交社 1977
穀川澈三の「茶道の美学に』によると、茶道の要素は、芸術の要素と、社交的な要素と利益要素と修行要素その4方面の要素から構成されている。そして芸術の隔離性を根拠に、茶道を身体の動きを媒介として出演の芸術を定義した。茶人と客が4枚半畳の茶室でお茶などの事をする時に、自然の世界と日常の世界をわざわざ隔てて、それによって茶道この伝統芸術の独立舞台を確立してということだ。
「茶道的哲学」 九松真一 理想社 1980
剩余内容已隐藏,您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容!
2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案
本研究のきっかけと目標
抹茶が好きだが、日本は昔か茶ノ木もお茶を飲む習慣もない。飲茶習慣は七、八世紀の平安時代から始まった。当時の空海、最澄禅師は中国大陸から日本に持ち帰った。「茶道入門』によると、749年孝谦天皇は奈良大寺で僧侶五千人を集めてお経を読んだ。その後茶によってねぎらった。お茶が日本に伝わったばかり、貴族や高僧や天皇だけ楽しめた。鎌倉時代に栄西が中国から禪宗を持ち帰ったと同時に、新しいお茶の作り方も持ち帰った、それが抹茶だった。
本研究の方法
剩余内容已隐藏,您需要先支付 10元 才能查看该篇文章全部内容!立即支付
课题毕业论文、开题报告、任务书、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。